丈瑠に言われてみれば、そんなことがあったような気もしてくる彦馬だった。
顎に手を当てて考え込む彦馬を見て、丈瑠はまたも反対側に身体を向けて、掛け布団の中に潜り込んでしまった。
「殿!」
それを見た彦馬が声をかけるが、丈瑠は応えない。
「とーの!」
「爺はなんでも忘れてしまうんだろ」
重ねて呼びかけると、丈瑠が布団の中で呟く。
「なんと。他にも爺が忘れてしまっていることがあるのですか。ならば………」
彦馬は布団の中の丈瑠に話しかける。昔に戻ったようだ、と微笑みながら。
かつて、思ったように剣やモヂカラの稽古が捗らなくて、拗ねて布団の中に潜ってしまう丈瑠に、こんな風によく話しかけたものだ。
「爺にお聞かせくださいな」
彦馬がそれだけ言って布団の横に座っていると、沈黙に耐えられなくなった小さな丈瑠はやがて布団から顔を出して、彦馬を見上げるのだ。しかし、今の大きな丈瑠は布団に潜ったままだった。それを少し寂しく感じた彦馬は、薄く笑みを浮かべる。このような感情は、本当に闘いが終わったから、湧いてくるのだろうと実感したのだ。
彦馬が丈瑠に求めた、揺るがない強さのシンケンレッド。
そんなものは幻想でしかない。初代志葉烈堂はそうだったと言われているが、それだとて真実はわからない。古文書の中でしか、その姿は知れないのだから。後世に残すための資料を記録した経験を持つ彦馬は、それを痛感していた。
闘いの最中での個々人の思いなど、文書に残すことはないのだ。どんなに辛く、どんなに精神的に追い詰められた闘いであっても、結果が良ければそれしか記さない。闘いの中での、侍たちの葛藤は考慮されない。
だから、フィジカル的にもメンタル的にも、揺るがない強さを持ち続けられたシンケンレッドなど、本当はどこにもいないのだろう、と彦馬は思っていた。十七代目当主の時もそうだった。それを知っていてなお、丈瑠にはそれを求めた。
早く大きくなって。
早く強くなって。
今よりももっと大きなモヂカラを使えるようになって。
そんな風に、ただひたすら、丈瑠に強さだけを求め続けていたのに。今は、丈瑠が強く大きくなったことを寂しいと感じるとは。
あまりに感傷的な自分に苦笑いをしながら、丈瑠の横に座る彦馬。相変わらず、布団から出る気配のない丈瑠。開け放たれた障子の向こうには、眩しい光があふれている。
静かで平和な時が、志葉家に流れる。
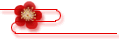
暫くそうして丈瑠のふくらんだ布団を眺めていた彦馬だが、そろそろ黒子たちとの午前の打ち合わせの時間だった。寝てしまったかも知れない丈瑠を起こさないようにと、そっと立ち上がり部屋を出ようとした彦馬の背中に、ぽそりと声が掛かった。
「腰は………」
彦馬が振り返るが、布団から丈瑠の頭は出ていない。
「腰は大丈夫なのか」
出てはいないが、しっかりとした声が、布団の中から聞こえてくる。彦馬はまたも苦笑いをした。
「もう大丈夫ですぞ。今日は暖かくなりそうですしな。春もすぐそこでしょう。殿の好きな鶯も、今日こそは庭に下りて来るやも知れませんな」
彦馬がそう言うと、丈瑠が黙った。話は終わったと思った彦馬が廊下に足を踏み出す。廊下の板がぎしりと鳴ると、再び、丈瑠が呟く。
「うぐいすが好きだったのは俺じゃない」
唐突な話に、彦馬が足を止めて、振り返る。
「うぐいすが好きだったのは………爺だ」
「………はっ?」
問い返す彦馬に、布団がもぞもぞと動いた。
「爺は、本当に何でも忘れるんだな。志葉家に来て初めての冬に、爺は俺に言ったんだ。うぐいすは春告鳥と言って、春を連れてくる鳥だから早く啼くといい………と、いつもいつも、本当にしつこいくらい言っていたんだ」
それでも丈瑠は、未だに布団の中に潜ったままだ。
「それは………」
十七年前。冬に向かいドウコクとの闘いが激しさを増していた頃。幼い子供が庭に出るのも危険で、部屋に閉じこもるしかなかった頃。
春になれば………その頃には、戦況も良くなっているのでは、という微かな期待と共に、そんなことを言ったかも知れない。
けれど春を迎えずして、十七代目当主はドウコクの前に敗れた。その後、熱に倒れた丈瑠が回復する気配もなかったため、せめて春になり暖かな日差しが射す頃になれば、丈瑠も少しは良くはならないかと言う願いを込めて。幼い丈瑠の枕元で、意識のない丈瑠に、そんなことを語りかけていたかも知れない。
「それに爺は言っていた。うぐいすの漢字には、火が二つも入っている。だから、俺の鳥だ………って」
彦馬は微笑んだ。
意識のない丈瑠の傍でただ黙って座っているよりも、何かしら丈瑠に話しかけた方がいいのではないか、と考えた彦馬は、そんなことも言った。いつも丈瑠に『火』の漢字の練習ばかりをさせていたので、『火』の漢字は知っている丈瑠に、鳥の上に火を二つ書いて鶯になるのだと。だから、鶯は『火』の文字を受け継ぐ、『火』の化身であるシンケンレッドになる丈瑠に近い鳥なのだと。
単なる戯言、呟きだった。意味などない。しかし、それを丈瑠は、夢うつつの中でしっかり聞いていたのだ。
「だから俺は………」
丈瑠が最後に呟いた時、彦馬の耳に高い音が聞こえた。
ホーホケキョ
彦馬は思わず、庭を振りかえる。
ホーホケキョ ホーホケキョ
鶯の啼き声はとても大きい。今も、丈瑠の寝室の奥までも、はっきりと聞こえたことだろう。彦馬の顔も自然と綻ぶ。
「殿。ちょうど話をしておりましたら………」
彦馬は廊下に立って庭に身体を向けたまま、丈瑠に話しかける。
「鶯ですぞ。裏の竹林から下りてきたのですな」
ホーホケキョ
はっきりと明確に啼く鶯。その啼き声を聞くだけで、本当に春がやって来たような気分になってくる。先ほどまでの感傷的な気持ちも吹き飛び、晴れ晴れと爽やかな気持ちに、全身が満たされる。
「やはり、いいですなあ。鶯は。確かに爺は、鶯が好きですな。漢字に『火』が入っている、殿の鳥でもありますし。爺の心にも身体にも、なにやら新しい力が湧いてくるような気がしますし………」
「だから!!」
彦馬の言葉に重なって、鶯と同じくらい大きな声が背中でした。驚いて振り返ると、丈瑠が布団の上に起き上がっていた。
「殿!?」
驚く彦馬に
「だから………だ!」
そう言って丈瑠は唇をかむと横を向いてしまう。丈瑠の言葉が理解できず、ぽかんとする彦馬の背中に、また鶯の声が鳴り響く。
ホーホケキョ ホーホケキョー
ホーケキョ ケキョ、キョキョ
いつの間にか、鶯は二羽になっていた。片方の啼き方はまだ幼いが、それもまた、早春らしい。
そう言えば、志葉屋敷で一番初めに鶯が啼きはじめるのは、いつも、この丈瑠の部屋の前だ。別に裏山に一番近い訳でもないのに、鶯は必ず、この庭から啼き始める。そして、その最初の鶯の啼き声は、いつも拙くない。完成された啼き声だった。やがて、それに誘われるように、まだ上手く啼けない鶯が、この庭にやってくる。
毎年、必ずそうだった。そう。丈瑠が殿になった、あの春から、毎年必ず。
「もしかすると………」
彦馬の頭を、今初めて掠った考え。
「殿………が?」
そんなことを考えたこともなかった。何故、志葉屋敷の中でも奥まった丈瑠の庭でだけ、いつも最初に鶯が啼くか、など。
「それも、爺のために殿は………」
彦馬の自惚れなどではないだろう。彦馬が最後まで言わない内に、丈瑠がぷいと横を向いた。
「最初の冬だけじゃない。爺が寒いだの、腰が痛いだのって、毎冬言うから、俺は!!」
それきり黙りこんでしまう丈瑠。しかしそれを聞いた彦馬は、鼻の奥が痛くなってくるのを止められない。
ドウコクと十七代目当主との闘いで、モヂカラが何なのかを理解できた丈瑠。だから彦馬の、丈瑠に『火』のモヂカラを覚えてほしいという願いの意味も理解できた。しかし、まだ熱の下がらない丈瑠には、大きな『火』のモヂカラを発現する力はなかった。それでも、寝る間も惜しんで、自分の看病をしてくれる彦馬。しかし丈瑠が心配なあまり元気のない彦馬を、丈瑠は少しでも喜ばせたかった。
彦馬が望むのと同じ『火』の漢字が入っている鳥なので、これはきっと『火』のモヂカラを使うのと同じことだろうと思った。だから彦馬に背負われて庭に散歩に出た時に、モヂカラで鶯を出してみた。彦馬はそれを見てとても喜んだし、大声で啼くモヂカラの鶯は、すぐに本物の鶯を裏山から呼び込んでくれた。本当は、彦馬が喜んだのは、鶯の啼き声に丈瑠が反応した、そちらだったのだが、丈瑠にはそれがわからなかった。
それ以降、彦馬は鶯が好きだと言うことが刷り込まれた丈瑠は、彦馬の喜ぶ顔がみたくて、鶯が呼べそうな時期を見計らっては鶯を出していたのだ。あまり早すぎると、呼ばれてくる本物の鶯が死んでしまうので、それにも気を使っていた。
丈瑠にとって、なにより大事な彦馬。その彦馬を思う気持ちを出したモヂカラ。丈瑠にとってのモヂカラは、いつもそのようなものだった。
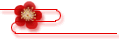
十七年の間、丈瑠の傍を片時も離れず、丈瑠を育ててきた彦馬だったが、気が付かないこともあったのだ。それも、いろいろと。
シンケンレッドとなり、外道衆と闘うようになり、攻撃的な『火』のモヂカラを使うようになった丈瑠。今では、ナナシの100匹程度、一瞬で焼き尽くせるほどのモヂカラを持っている丈瑠だ。
そんな丈瑠を毎日見ながら、もっと強く、もっと大きな力を、と望んでいた彦馬。それは、丈瑠が外道衆との闘いに倒れ、傷つかないようにとの願いからだったが、そのために彦馬は誤解してしまっていたのだろう。
かつて、志葉家に入ったばかりの頃の丈瑠と、今の丈瑠と、どこが違うというのだろう。
丈瑠は今でも、あの頃の心を持っている。丈瑠の使うモヂカラは、外道衆と闘うために大きくなったが、それは、人を守るためなのだ。闘う力ではない。人を守るための力。人を幸せにするための力。
十臓と最後に闘った時には、確かに足を踏み外しかけたかも知れない。けれど、丈瑠はいままでずっと、人々が幸福であるようにと、それだけのために、自分を犠牲にして闘ってきたのだ。
丈瑠の今までの人生には、嘘が多かったかもしれない。見ようによっては、嘘だけとも言えるのかもしれない。
けれど、この丈瑠の気持ちには、どんな嘘もない。偽りの気持ちでは、とうてい、ここまで来ることはできなかったはずだ。丈瑠は、彦馬が思うよりもずっと健全に、ずっと強く育っていた。
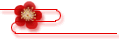
「爺は………」
嬉しいです。と言いたかったが、言葉が詰まって言えなくなってしまった。
布団の上に座る、武者人形のように凛々しい丈瑠。
肩や袖口から見える包帯姿は痛々しいが、それでも、誰よりも勇敢で強いシンケンレッドだ。そして、彦馬にとっては、完璧な志葉家十九代目当主でもある。今改めて、彦馬はそう思った。闘うだけの志葉家当主ではなく、この世を守るための志葉家当主として、丈瑠は完璧にその役を担えるように育ったのだ。
その志葉丈瑠の、また新たな人生がこれから始まる。十七年前と同様に、早春を迎えたこの日に、この同じ志葉家で。
自分を守ることすらできなかった十七年前も、この世を外道衆から守りきった今も、変わらぬ気持ちを持ち続けられた丈瑠。その本当の意味での強さを、彦馬は今更ながらに、嬉しいと思った。
十七年前からの闘いの余韻が、外道衆との闘いという意味でも、丈瑠の境遇と言う意味でも、また切り替えられない気持ちという意味でも、これからも尾を引き続けるだろう。それはきっと長い年月、消えることはない。
それでも、ひとつの幕は下りたのだ。そしてこれからの、今までよりももっと長い時間、丈瑠を見守り続けるのも、ここまで丈瑠を連れてきてしまった自分の役目。彦馬はそう思った。
「爺は………殿に元気をもらいましたから、まだまだ殿のお傍にお仕えしますぞ」
彦馬がそう断言すると、丈瑠のほおが少し紅潮した。
「………そ、そっか」
丈瑠はぶっきらぼうにそれだけ言うと、また庭に背を向けて、布団に潜り込む。
ホーホケキョ ホーホケキョ
ホケッ ホーホケッキョ
陽射しが眩しい、奥屋敷の庭。
その梅の木で、丈瑠のモヂカラの鶯と、裏山から誘われて出てきた鶯が啼いた。
ホーホケキョ ホーホケキョ
ホーホケッ ホーホケキョ
それが十七年前から続く、志葉屋敷に春の訪れを告げる、いつもの光景だった。
小説
終わりまで読んでいただきありがとうございました。
まるで爺殿(笑)でしたか?
爺が殿大事なのも、殿が爺大好きなのも、
公式設定ですものね〜♪
殿が結婚しても、爺は引退しないでしょうね。
良かったね、殿。
爺がいなくなったら、殿、泣いちゃいますよね、きっと。
もし、お気に召して頂けましたら
拍手・感想など頂けると、本当に嬉しいです♪
あるいは、ご要望などもあればどうぞ。
2010.04.10