「殿ー!」
突然の大声に、縁側に座っていた丈瑠は驚いて顔を上げた。
「殿ーー!」
今までだったら、彦馬のこのような叫びは、丈瑠が外道衆と闘うために出陣する必要があることを知らせるものだった。
外道衆の大将であるドウコクは既に倒した。そのぎりぎりの闘いから、まだ一週間しか経っていない。三途の川の水も激減したはずだ。こんなに早く外道衆が出てくるはずがない。そう頭では分かっていても、彦馬のこんな声を聞くと、丈瑠の身体がかっと熱くなる。
もう何年も、ずっと繰り返してきたこと。だから、身体が自然と反応するのだ。
かつて、こんな身体の反応が、丈瑠には疎ましい時期があった。
敵に身構える………と言えば聞こえがいいが、丈瑠には自分の身体の反応が、小動物のそれと同じだと思えて仕方がなかったのだ。獰猛な肉食獣に狙われた小動物の、それと同じ。
志葉家当主として、外道衆を倒すことを運命づけられたシンケンレッドの丈瑠は、勇猛果敢な侍であることを求められてきた。例えれば「獅子」のような侍であることを求められてきたのだ。何しろ、シンケンレッドの受け継いできた文字は「火」。そして、その火のエンブレムは獅子折神なのだ。今まさに、丈瑠の手のひらの上で動き回っている赤い折神が、それだ。それなのに、闘いに向かう丈瑠の身体は、獅子ではなく、獅子に狙われた小動物の方の反応になってしまう。
この身体の反応を感じるたびに、丈瑠は思わずにはいられなかった。
やはり、自分は違う。自分には、シンケンレッドの資格がない。
それは、丈瑠に闘いへの恐怖心を呼び起こす。けれど、闘いは待ってくれない。そして現代で、まがりなりにもシンケンレッドと名乗り、外道衆と闘えるのは自分一人しかいない。だから丈瑠は、人間なら当り前に湧き上がる感情を押し殺し、いつもいつも死を覚悟して闘いに赴いていた。
初めは、一体きりのナナシでも、なかなか倒せなかった。息も絶え絶え、傷だらけになりながら、やっとのことでナナシを倒しても、その後、自分も寝込んでしまう始末。そんなことを繰り返して、いつか気がつけば、複数のナナシを相手にできるところまで来ていた。しかし闘いの後で、彦馬が丈瑠の闘いぶりを讃えても、丈瑠の心に余裕は生まれなかった。自分が強くなったとは、感じられなかった。
丈瑠がその頃、闘いの後に感じていたのは、生き延びた、今日も死ななかった、という、ただそれだけだった。そして、また次の闘いのために、日々を生きる。この世を、人々を守ること。それが、志葉家当主としての務めだと信じて。
「決して逃げるな。外道衆からこの世を守れ」
そう言って果てた父との誓いを果たすために。ただそのためだけに。
そこには、自分の未来に対する夢も希望もなかった。
使命を果たすためには、ナナシ如き相手に死ぬことはできない。死なないためには、闘いがない日でも、稽古を欠かすことはできない。真実、死と隣り合わせの毎日。やがてそれが本当に丈瑠の日常となった時、丈瑠の心のどこかが麻痺して行った。
そうでなければ、生き抜けなかった。外道衆に殺されなくても、自らの心に潰されてしまっていただろう。
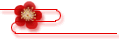
「殿!!何をしておられるのですか!!」
表屋敷側の棟に続いている廊下をどしどしと踏みならしながら、丈瑠の座っている奥屋敷の縁側に向かって、彦馬が駆けつけてくる。丈瑠は手のひらの上で遊ばせていた獅子折神を、瞬時にエンブレムに戻して握りこんだ。そして、僅かに腰を浮かせる。いつでも、飛び出せるように。
「とーのー!」
彦馬の低音だがよく通る声が、奥屋敷に響き渡った。丈瑠の険しい顔に、彦馬が叫んだ。
「爺がちょっと出かけている隙に、お部屋から抜け出されて!!お布団で休まれるように言っておきましたでしょうが!!!」
丈瑠の表情が一気に緩む。
「なんだ。外道衆じゃないのか」
丈瑠は、浮かせていた腰を、再び座布団に戻すと、彦馬から眼をそらした。
丈瑠の横までやって来た彦馬が、丈瑠の傍らに置かれたものを注視した。そこには、盆に載せられたおしぼりとお茶があった。彦馬の顔がさらに渋くなる。視界には入らないが、そこここにいるであろう黒子が首を竦めているのが、丈瑠には見えるようだった。
「いけませんぞ!いったい、どれほどここに居られたのです!?」
「うるさい」
丈瑠は間近で文句を言い続ける彦馬に、小さな声で、しかしぶっきらぼうに応えた。
彦馬の大声が、外道衆の出現によるものではなく、単なる説教と分かった瞬間に、丈瑠はまともに相手をする気をなくしていた。そんな丈瑠の態度に、彦馬は、少しだけ瞳を見開いた。しかし、すぐに構うことなく、大声を続ける。
「うるさいではありません!!」
彦馬は丈瑠の腕を取って、引き上げようとした。
「お風邪を召されて、お部屋でお休み中のはずです。こんな縁側で、寒風にさらされて、こじらせたらどうするのですか!!」
丈瑠は、その彦馬の腕を軽く振り解くと、そのまま傍らの茶碗を手に取り、茶をぐいっと喉に流し込んだ。布団から出てきて寝巻のまま、縁側から動こうとしない丈瑠への、黒子のせめてもの心遣いの茶は、まだ十分に暖かかった。
「とーのーーー!!昼過ぎまで熱が高かったのをお忘れか!?」
彦馬の言うことを聞こうとしない丈瑠に、彦馬が呆れた声を出す。
「わがままも、いい加減にしませんと」
「わがままじゃない!熱ももうない!!」
丈瑠がそれを遮る。
「わがままではないと申されるのでしたら、それでは一体、殿はここで何をなさって」
「うぐいすだ!!」
丈瑠が、我慢しかねた様子で、怒鳴った。
「は?」
しかし彦馬には、通じない。彦馬は首を傾げただけだった。
いつものことではあるが、そうしてみると、丈瑠も声を荒げた自分が、きまり悪くなってしまう。
「うぐいすの啼き声を………」
エンブレムを握りしめながら、丈瑠は横を向いて、小さく呟く。
「聞いていたんだ」
思わず彦馬は黙り込んだ。
180cmを超えるほどにまで大きく成長した丈瑠。
しかし彦馬には、こんな時の丈瑠は、あの小さかった頃の丈瑠と同じように見えてしまう。
「………鶯………ですか」
一旦そう感じてしまうと、彦馬の声も自然と穏やかにならざるを得ない。それに、丈瑠がほんのわずか頷いた。十七年前のあの幼子の頃のように。
「鶯………」
そんな丈瑠の仕草に胸に突き刺さるものを感じて、彦馬は顔をそらすように、縁側の前に広がる庭を見つめた。
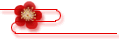
三百年の昔から続く志葉家の、広大な屋敷。
都心にあるにも関わらず、昔からの大名屋敷をそのままに保ってきた志葉家の敷地は、山あり、谷あり、雑木林も、自然の湧き水による泉も池も小川もあり………と、考えられないほどの広さだった。
その表門から遥かに離れた屋敷の奥深くに、丈瑠の居室はあった。侵入者から志葉家の当主を守るために、建物内からでも、庭伝いでも、表から複雑に入り組んだ先にある奥屋敷。そこは、外の世界とは完全に遮断された閉鎖空間だ。
しかし、屋敷のあちこちに設けられた趣向の凝らされた日本庭園や自然の景色が、それを感じさせない。手入れが行き届いたそれぞれの庭は、季節ごと楽しめるように、多くの種類の木々や草花で彩られ、築山や池、あずま屋に灯篭なども造られていた。また、夏には川沿いから上がってくるホタルが夜の庭を彩り、秋冬には豊富な木の実を求めて様々な鳥が訪れた。
丈瑠の部屋の前のこの庭もそうだ。春に向けて、蕾が膨らんだ木々や草花がたくさんあった。もう少し陽射しが暖かくなってきたら、そこここから芽吹きが始まるのだろう。もちろん、裏山の竹林から鶯だって下りてくるに違いない。
志葉屋敷の中でも特にこの丈瑠の部屋の前庭で、鶯がよく啼くということは、志葉家の人間にとっては常識だった。
そうはいえども、今は二月も半ば。
空気も水も凍えるほどに冷たい。木々も草花も、まだ眠っている状態だ。
普段は日当たりのよいこの庭ですら、今にも雪が降り出しそうな曇天では、まだまだ鶯の声など望むべくもない。
それでも丈瑠の言葉を尊重して、暫く啼き声を待ってみた彦馬だったが、奥屋敷には鶯の啼き声どころか、物音ひとつ聞こえてこなかった。
「爺には、聞こえませぬが………」
言いながら丈瑠に目をやると、丈瑠は相変わらず横を向いたままだ。そんな丈瑠の子供っぽい仕草が、彦馬の胸を切なくする。
これが一年前だったら、彦馬の胸を去来した感情は、もっと違う、そしてもっと切実なものだっただろう。しかし、一年前とは全く違う状況の今、彦馬は、自分が随分と感傷的になっているのを、はっきりと感じていた。
彦馬はそんな感情を振り払うように、胸の前で腕を組んで、空を見上げた。
二月の空は、どんよりと雲が垂れこめていた。
「まあ、梅もちらほらと咲き始めたところですし、今日は気温も低くて無理でしょうが、そろそろ鶯も啼きますかな」
「でも、啼いてた!!」
丈瑠が再び怒鳴る。そして怒鳴った瞬間に、しまったと言う顔をする。そんな丈瑠を見て、彦馬はため息をついた。彦馬だけではない。丈瑠もきっと、感傷的になっているのだろう。しかし、それも仕方がないことだと彦馬は思う。
「わかりました」
彦馬はそう言うと、丈瑠の腕を今度はそっと取った。
「殿がお休みになるお部屋の戸を開けておきましょう。そうすれば、雲が切れてくれば、陽射しも入りますし、鶯が啼けば、その声も聞こえるでしょう」
丈瑠が唇を尖らせて、彦馬を見上げるが、彦馬は平然としていた。
ここまで言われては、丈瑠も従うしかない。しぶしぶと丈瑠は立ち上がった。
素直に立ち上がった丈瑠の手を取った彦馬は、再び渋い顔をする。
「こんなに冷えきって………」
丈瑠はぷいっと横を向きつつも、彦馬に手を取られたまま、縁側から寝室に入った。
古い日本家屋特有の、薄暗い部屋の中央に、布団が敷いてあった。
丈瑠が部屋に戻ると、どこからともなく黒子が現れて、丈瑠を布団に寝かせる手伝いをする。
ずっと、そんな風にして生きてきた。だから慣れてしまったのだが、きっとこれは、かなり奇妙な光景なのだろう。シンケンジャーのみんなと接した後だから、よく分かる。
そして、もうひとつ、思わずにはいられないこと。本当は、自分にはこうされる資格がなかったはずなのに。
今、十七年の時を経て、状況が激変して、丈瑠の立場もまた変わった。年が明けて以降のことを思えば、今だに自分が、この屋敷にこうやって居ることの不思議を思わずにはいられない。それが、長い目で見れば、自分にとって良かったのか、悪かったか。その結論はまだ出ていないのだけれど。
丈瑠はそんなことをぼんやり思いながらも、黒子のされるがままだ。本当は、十九代当主に就いた後、黒子や彦馬に世話を焼かれるのに苦痛を感じた。しかし、そんな丈瑠を家臣たちは認めなかった。だから、十七年前からと変わらない生活を、続けることになってしまった。彦馬の前では、特にそうなる。そうしないと、彦馬が哀しそう目をするから。
丈瑠が布団に横になったのを確認した彦馬が、黒子に部屋の障子を全開にさせた。途端に、丈瑠の寝室は明るくなった。
「これで、大人しくお休み頂けますな」
念押しされて、丈瑠は無言のまま掛け布団を頭の上まで引きずりあげた。
「約束しましたぞ?」
彦馬は黒子を部屋から出した後も、丈瑠の布団の傍らに座り続けた。彦馬は、丈瑠が眠るまで見張っているつもりなのだろう。丈瑠は布団をかぶったまま、息を殺す。二人の我慢比べの様相を呈し始めたころ、それは起こった。
小説 次話
2010.03.03