「っつ!!」
彦馬の悲痛な声ならぬ声に、布団に潜り込んでいた丈瑠が、何事かと顔を出す。
「爺!?」
丈瑠の布団の傍らで、腰に手をやっている彦馬を見て、丈瑠は思わず布団を跳ね除けて起き上がった。
元気で丈夫な彦馬だったが、持病の腰痛に悩まされるようになったのは、ここ数年のことだ。それでも彦馬は、丈瑠の外出には黒子と共に必ず付き添ってくれていた。それは、外道衆との戦闘も同様だった。なんだかんだと文句を言いつつも、たった一人での外道衆との闘いの後、彦馬の顔を見れば、それだけで安心できる丈瑠だった。
その彦馬が、この一年ばかりはぱったりと丈瑠の闘いに付き添わなくなった。シンケンジャー結成以降のことだ。シンケンジャーの侍たちとやっていくのに、いつまでもお目付役の彦馬が傍にいたのでは、丈瑠がやりにくいだろうとの、彦馬の配慮だった。また、本格的なドウコクとの闘いが始まったことにより、彦馬にはやらねばならないことが増えた。闘いを有利に進めるための過去の文献調査、現状の情報収集、黒子の手配等々だ。さらには、彦馬から見ればまだまだ未熟な侍たちの生活指導や精神ケアも彦馬がしなければならない。
そういうことを考慮すると、丈瑠に付き添わなくなっても、この一年の彦馬の負担は、むしろ前より増したと言える。
丈瑠は闘うだけだ。けれど彦馬には、他の全てをやって貰っている。彦馬に無理をさせている。これでは、彦馬が倒れてしまうのではないか。そうは思っても、自分自身にも余裕がない上、今まで全てを彦馬に頼り切っていた丈瑠には、何もできなかった。せめて外道衆との闘いくらいは、彦馬に面倒をかけまい。そう思いつつも結局、シンケンジャーの誰よりも先頭に立って闘っている分、先に倒れてしまう丈瑠だった。それでまた、彦馬に心労をかける。そんな繰り返しの一年だった。
その上、最後の最後には、彦馬にもシンケンジャーのみんなにも、信じられないほどの心配をかけた。
精神的ストレスでも、腰痛は悪化するのだろうか。そうだとしたら、彦馬の腰痛がここ一年で酷くなったのは、絶対に自分のせいだ。
丈瑠はそう思っていた。
丈瑠が起き上がったのを見た彦馬が、丈瑠を止めようとして無理な体勢になり、
「ううっ!」
と唸ると、再び畳に崩れこんだ。
「爺!馬鹿!!」
「な、何を申されますか。馬鹿とはなんです!?」
布団の上に起き上がり彦馬を覗き込む丈瑠を、顔を痛みに歪めつつ彦馬が叱る。丈瑠は呆れる。
「俺のことより、自分の腰のこと心配しろ!!ほら肩を!!」
彦馬に貸そうと差し出した丈瑠の手は、彦馬の鋭い視線に睨まれただけだった。
「爺はいいですから!!殿はお休みください」
「何言ってるんだ!早く横にならないと悪化するぞ。それに、一人じゃ歩けないだろうが!?」
丈瑠は彦馬の肩に手をまわそうとする。それを彦馬がまたも遮る。
「爺!いい加減にしろよ!!」
先ほどと立場が入れ替わり、今度は丈瑠がしびれを切らして叫ぶ。
「おい!誰か!!爺を部屋に連れて行ってやれ!」
丈瑠の呼びかけに、瞬時に廊下に黒子が現れ彦馬の傍に寄るが、彦馬はそれすらも、首を振って遮った。
「爺!!」
「殿はとにかくお休みください!!爺はそれをを見届けてからでないと、この部屋を動きませんぞ!!」
彦馬は頑として言うことをきかない。
丈瑠はため息をついた。
「あのなあ、爺。俺の風邪なんて、たいしたことないだろう?それより、自分の腰を心配しろよ。今、爺の部屋に布団敷かせるから、ちょっと待ってろ」
「殿がお休みになるのが先です!!」
丈瑠を部屋から出すまいとする彦馬に、ついに丈瑠は強硬手段に出た。
「わかった!それじゃあ、俺の布団で悪いが、そこに寝てろ!!どうせ、ここから一人で動けないんだ、それでいいだろ!!」
「な、なんですと!?冗談ではありません」
「そうだ。冗談じゃない!」
丈瑠はそう言うと、彦馬を無理やり、自分が今まで寝ていた布団に、押し込んだ。
「とーーーーのーーーー!!」
黒子が目を丸くしている横で、丈瑠がにやりと笑う。
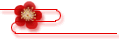
丈瑠が休んでいることを監視し続けたい彦馬。
彦馬の腰が心配で、彦馬を横にならせたい丈瑠。
結局、丈瑠が黒子に指示した結果、今、丈瑠の寝室に二組の布団が敷かれ、そこに丈瑠と彦馬が並んで寝る………という状況に落ち着いた。
「あり得ませんぞ!!こんなこと!!」
布団に横になっても文句を言う彦馬に、丈瑠は頭が痛くなってくる。それと共に、不思議な感情が丈瑠の内に湧き上がってきた。
この同じ寝室。
二つ敷かれた布団。
丈瑠は天井を見つめながら、脳裏に蘇って来る遠い昔の光景を見つめる。
「………あっただろ」
丈瑠はため息とともに、彦馬に応えた。
「何ですと?」
怪訝な顔を向ける彦馬に、丈瑠は背を向けた。
「昔、あっただろ。この部屋で、爺と寝たこと。いや、同じ布団で寝たことだってある………」
丈瑠の言葉に、一瞬彦馬の顔が曇った。
「そう………でしたかな」
彦馬の声が低くなる。
「憶えて………いらっしゃいましたか」
躊躇いがちな声が、寝室に消えて行く。
「お小さい頃のことでしたので………」
丈瑠は、彦馬に背を向けたまま、庭を見ながら答えた。
「爺はよく俺に言っていたじゃないか。父の最期の言葉を忘れていないだろうな!って。同じ頃………だろ。憶えているさ」
「そう…でしたか………」
彦馬の声は、腰の痛みを耐える時よりも、もっと沈痛なものに聞こえた。
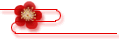
それは、今から十七年前に遡る。
丈瑠を志葉屋敷に迎え入れることが決まった時、すでに志葉家十七代目当主と外道衆の闘いは佳境に入っていた。そのため、十八代目を担うことになる幼子に、気持ちを向ける余裕のある大人は、志葉屋敷の中では、丈瑠の養育係に任命された日下部彦馬以外にはいなかった。
圧倒的な力を誇る血祭ドウコクに勝つ方策が見つからない悲壮感漂う志葉家。その大人ばかりの屋敷の片隅で、幼い丈瑠は、新しい人生を歩み出すことになった。
可愛がってくれた肉親や、住みなれた家から離れること。それだけでも、幼い子供には辛いことだ。だが丈瑠の場合は、それだけでは済まなかった。丈瑠が志葉屋敷に来たその日から、丈瑠が次期志葉家当主を担うための闘いも始まったのだ。そして、それは丈瑠だけの闘いではなく、丈瑠の養育係である彦馬、ひいては衰退激しい志葉家の、血筋を残すための最後の闘いでもあった。
丈瑠はまだ幼児でひらがなひとつ読めなかったが、毎日、剣道と書道の稽古を強要された。さらに、朝の挨拶から始まって、箸の上げ下ろし、言葉づかい、姿勢、立ち居振る舞いまで、ひとつひとつを、彦馬に志葉家当主にふさわしいものへと矯正させられる。
それほど活発な子供ではなかった丈瑠は、反抗する術もなく、ただ彦馬に言われるがままに、志葉家の生活に飲まれていった。
丈瑠には、何故自分の生活が激変したのか理解できていなかった。いつか元の生活に戻れる日が来るかも知れないと淡い期待を抱きながら、彦馬との息の抜けない生活に馴染んでいくしか、幼い丈瑠が生きる道はなかった。
一方、彦馬は手加減をしなかった。
丈瑠を志葉家次期当主に仕立て上げるということは、前代未聞の大仕事で、手加減してできるようなものではなかったのだ。その最大の難関が、モヂカラの習得だった。
志葉家の当主は「火」のモヂカラを使う。これが使えなければ、志葉家の当主、そしてシンケンレッドとしては成り立たない。外道衆と闘うどころか、変身すらできないからだ。
十八代目を担う者として志葉家に入っただけあって、確かに丈瑠にはモヂカラの才能があった。しかし丈瑠のそれは、彦馬の眼には、志葉家当主としてのものとは質が違うような気がしてならなかった。丈瑠のモヂカラは、丈瑠のモヂカラとして伸ばしていくことができれば、かなりのものになるだろう。幼い丈瑠が意識せずに繰り出すモヂカラは、外道衆との闘いに役立つかはともかく、侍の血筋の子供と比較しても、驚くほど多彩だったのだから。
しかし彦馬は、丈瑠が本来持っているモヂカラの才能を伸ばす方向には力を注がなかった。いや、注ぐことを許されなかった。とにかく、丈瑠に「火」のモヂカラを習得させねばならず、ひたすらその訓練に明け暮れた。その訓練は幼児にとっては苛烈を極め、かえって丈瑠の本来のモヂカラの才能を潰してしまう可能性もあった。それでも仕方ないと彦馬は思った。丈瑠が志葉家の十八代目当主と分かれば、外道衆が丈瑠を標的にして襲ってくるのは明らかだ。その時、丈瑠がシンケンレッドになれなかったら、丈瑠は外道衆に殺されるしかないのだ。
それでは、丈瑠はただの人身御供、生贄でしかなくなってしまう。そんなことのために、丈瑠を育てているのではない。丈瑠を死なさないためには、丈瑠がどんなに辛い想いをしようとも、本来の才能を潰してしまうことになろうとも、丈瑠に「火」のモヂカラを覚えさせるしかなかったのだ。
この世界を守るため。志葉家の血筋を絶やさぬため。それは、その通りだったが、それだけでなく丈瑠自身のために、丈瑠が志葉家十八代目当主、シンケンレッドとして立派に育つように、日下部彦馬は鬼にもなろう。
彦馬はそう硬く決心していた。
そこまでの決意で彦馬は丈瑠に接していた。しかし、幼い丈瑠はなかなか「火」のモヂカラを習得することができなかった。
そんな内に日々も過ぎ、丈瑠が志葉屋敷に来て半年も経った頃、それは起きた。血祭ドウコク率いる外道衆が、志葉家を急襲したのだ。
その夜の闘いの展開は急で、彦馬が気がついた時には、外に逃げるには遅すぎる状況になっていた。
闘いに巻き込まれた彦馬や丈瑠だったが、凄惨な闘いを幼い丈瑠に見せることだけは避けたいと思った彦馬は、丈瑠を屋敷の奥に匿おうと思った。だが既に、屋敷中に発せられている闘いのモヂカラと悲愴な空気を、丈瑠は全身で感じ取ってしまっていた。
奥屋敷で呆然と立ちすくむ丈瑠を、彦馬が抱え上げて逃げようとした時、丈瑠が突然、彦馬の腕を逃れて駆け出した。普段はおとなしい丈瑠のその素早い行動に、彦馬は驚く。
ナナシが押し寄せる屋敷内。あちこちで上がる火の手。その中を潜り抜けるように駆けて行く丈瑠。寝室の隅の暗がりすら怖がる丈瑠が、広い屋敷の中、不気味な火の手がそこかしこに上がっている闇の中を駆けて行く。まだ若かった彦馬は、丈瑠の豹変ぶりに驚きつつも、必死に丈瑠を追った。やがて、丈瑠が表屋敷のある部屋に飛び込む。そこにいたのは、驚いたことに背中に何本もの矢を刺された丈瑠の父親だった。息絶える寸前の父親の手には、獅子折神が握られていた。
父親がどこで闘っていたのかなど知るはずもない丈瑠だったが、もしかしたら獅子折神が、次のシンケンレッドである丈瑠をここに呼び寄せたのだろうか。彦馬の驚きの気持ちをよそに、燃え盛る部屋で丈瑠は瀕死の父から、志葉家当主でありシンケンレッドの証である獅子折神を渡された。
「忘れるな」
最期の力を振り絞って、丈瑠の父親は丈瑠に告げる。
「今日からお前が、シンケンレッドだ」
志葉家に入ることになってから、何度も言われたその言葉。しかし、それまでの丈瑠には、その言葉の意味が分かってはいなかった。
「決して逃げるな。外道衆からこの世を守れ」
それだけの言葉を遺して、息絶える丈瑠の父親。燃え盛る室内。それを見つめる丈瑠。
彦馬は丈瑠を連れて逃げようとしたが、丈瑠はその場を動こうとしなかった。丈瑠は父親から渡された獅子折神を手に、ただじっと死んだ父親を見つめていた。
小説 次話
2010.03.03