その夜の闘いの結末は、悲惨なものとなった。
シンケンレッドを筆頭に、シンケンジャーの戦闘能力は消滅した。全滅したと言っても過言ではない状況だった。せめてもの救いは、志葉家十七代目当主であるシンケンレッドが亡くなる寸前に、不完全ながらも血祭ドウコクの封印に成功したことだった。
ドウコクの封印が解けるまでの時間とは言え、まずは、平和な日常が戻ってきたのだ。彦馬にとっては、幼い丈瑠をシンケンレッドとして闘えるまでにするための猶予ができたということだった。
そして幼すぎて実質が伴わないにせよ、また、単なる表向きにせよ、志葉家の十八代目当主に丈瑠が就いた日でもあった。すなわち、丈瑠が「殿」になった日だ。
十七代目当主からよく言い含められていた志葉家の殆どの家臣たちは、前当主の死の悲しみの中にあっても、幼い丈瑠に仕えることを納得した。
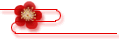
しかしその晩から、丈瑠は高熱を出し寝付いてしまった。そして、幾日たっても、その熱は下がることがなかった。
外道衆の襲撃の心配なく、平和な時間を持てるというのに、肝心の丈瑠が倒れてしまったのだ。
丈瑠の病の原因は、ひとつしか考えられなかった。外道衆との闘い。目の前での父親の死。その衝撃が、幼い丈瑠の精神に深い傷を残したのだろう。
彦馬は、丈瑠の枕元で考え続けた。
もしこれで、丈瑠が潰れてしまったら、自分は一体、何をしたことになるのだろう。志葉家の跡継ぎを作ることができなかっただけではない。幼い丈瑠の、始まったばかりの人生をめちゃくちゃにしてしまったことになるのだ。丈瑠自身に、何の非もないのに。むしろ、彦馬の教育に必死に付いてこようとしていたのに。
丈瑠のために、鬼にもなろうと決心していた彦馬だったが、とてもそのような状況ではなくなってしまった。彦馬は思った。絶対に、このまま丈瑠を潰してはならない、と。それは、丈瑠を志葉家に迎え入れることが決まった時の約束でもあった。
「今日から命を懸けて支え続ける。決して堕ちぬように。わが殿として」
彦馬は改めて、この約束の重さを知った。その十七年後に再び、彦馬はこの約束の重さが身に沁みることになるのだが、その時は、もちろんそのようなことを知る由もない。
決意を新たにした彦馬は、昼も夜も自分の身をなげうって、丈瑠の看病に明け暮れた。そして、意識があるのかないのか判然としない丈瑠に、それまでの半年を償うかのように優しく接した。夜は同じ部屋で眠り、食事は膝の上で彦馬が持ったスプーンで食べさせ、抱いて風呂に入れ、ぐずる時は背負って庭を散歩した。
立派な当主になってもらうためには、甘やかすことは禁物。そう信じていた彦馬だったが、明確な意識がない丈瑠には、どこまでも甘くなれた。
彦馬や黒子たちの献身的な看病にも関わらず、丈瑠の熱は下がらずに数ヶ月が過ぎた。もともと丈夫な丈瑠だったが、その体力はどんどん消耗して行った。十七代目当主を失ったばかりの志葉家家臣たちは、やがて、幼い十八代目当主の命までもが失われてしまうのかと、絶望的な気持ちになって行く。
しかし、丈瑠の病床に鶯の啼き声が聞こえるようになった早春のある日、突然、丈瑠の熱は下がったのだった。
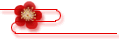
「確かにあの頃は毎日、この部屋で寝ておりました。あの頃は……大変でしたな………」
彦馬が呟く。
「殿がどうなってしまうのかと、爺も生きた心地がしませんでした」
あの頃から丈瑠が寝ていたのはこの寝室であり、彦馬が丈瑠を背負って散歩したのは、この寝室の前の庭であった。言いながら、彦馬はあることを思い出した。
「そう言えば、意識のない殿をおぶって庭を歩いていましたら、鶯がよく啼いていましたな。思えば、あの頃からですな。この庭に、鶯がよく来るようになったのは」
彦馬に背を向けたままの丈瑠の肩が、ぴくりと動く。それを見た彦馬の脳裏に、また、その頃のことが思い出された。
何時になったら意識が戻るのかも分からない丈瑠を背負って、庭を散歩していた頃。鶯が啼くと背中の丈瑠がぴくりと反応したのだ。それだからこそ、彦馬は、熱がある丈瑠を、何度も庭に背負って出たのだ。
「そう言えば、あの頃から殿は、鶯の啼き声がお気に入りだったですな。爺はすっかり忘れておりました」
あれから十七年の年月が流れた。この一年の激動で、その頃の記憶は色褪せたどころか、記憶の果てに消えようとしていた。しかし今、彦馬の脳裏にも、あの頃の光景が色鮮やかに蘇る。
「鶯のお陰か、殿の熱が下がった時には、黒子たちと祝いの宴を催したくらいです」
彦馬は横になったまま、目を細める。
その頃より、幼い丈瑠を命懸けで守ってきたのは、彦馬だけではない。丈瑠がシンケンレッドになれない間、丈瑠が自分で自分を守れない間は、丈瑠を外道衆から守れるのは、志葉家に残った者しかいなかった。シンケンジャーである侍たちの戦闘能力は失われてしまっていたし、その後継ぎはまだ育ってはいなかったのだから。
「………心配かけた」
彦馬に背を向けたままの丈瑠がぶっきらぼうに応える。それに、彦馬の顔が緩んだ。
決して個を出さず、会話せず、裏方に徹する黒子たち。それは、黒子としてではなく個人として屋敷を一歩出た時に、外道衆に狙われないための対策であった。反面、黒子と親しく口をきく機会のない丈瑠には、黒子の本心は見えなくなっていた。十八代目当主を名乗る丈瑠をどう思っているのか、丈瑠は気に病んでいたのかも知れない。
けれど丈瑠は、自分が十九代目当主に就くに際しての一連の騒動で、黒子たちが自分をどう思っているのか、十二分に理解しただろう。
丈瑠は、この世界を、そこに住む人々を、外道衆から守りきった。しかしまた一方で、丈瑠も守られていたのだ。シンケンジャーの侍たちにだけではない。十七年前から真実を知る大勢の家臣たちに。志葉家に残った者たちが一丸となって、丈瑠を守り育て上げて来たのだ。
「何の。それが爺と黒子の務めですからな」
そう応えながら、彦馬は思い出す。
「そう言えば、熱が下がった後も、殿は爺と一緒でないと寝られないとぐずられて………結局あの後、一年ほどは殿と一緒に寝ましたか」
体調が戻った後は、彦馬は丈瑠に、前と同じように厳しく接しようと思った。事実、丈瑠に対する躾も稽古も、前と変わらず、いや、それ以上に厳しくしたつもりだった。しかし、どこか気持ちの上では、大きく変わってしまっていた。同じことは、志葉屋敷全体、黒子たちの気持ちにも言えた。
早春の兆しを感じ取ったかのように、長く悲愴な空気に包まれていた志葉家に、柔らかく暖かな空気が流れ始めた。その中で、幼い子供の小さな願いに、誰もが寛容にならざるを得なかった。そして、その優しい空気が丈瑠の何かを変えたのか。
「あの後、すぐでしたかな」
彦馬や志葉家が望む攻撃的なモヂカラを、丈瑠が初めて使って見せたのも、その頃だった。燃え盛る………とまではいかないが、火傷する程度には熱い『火』のモヂカラを発現させたのだ。
「爺はそれが、どんなに嬉しかったことか。半年にわたる爺の苦労も報われたと思いましたぞ」
「………え?」
彦馬のその言葉に、丈瑠は布団の中で、思わず振り返った。
「殿!それはそうでしょう。殿に何よりも、『火』のモヂカラを覚えて頂きたかった爺ですから」
丈瑠の驚いた表情に、今度は彦馬が困惑する。本当は、言葉にしたよりも、もっと重い想いだった。丈瑠が「火」のモヂカラを使えないままだったら、どうなるのだろう。ずっと彦馬に圧し掛かっていた問題だったのだから。
「今から思えば、まだ殿は五歳にもならなかったのですから、『火』のモヂカラを覚えるのに数年かかっても不思議ではなかったのです。しかし、その頃はそういう余裕もありませんでしたからな。ドウコクとの明日をも知れぬ決戦を前にして、一刻も早く殿に『火』のモヂカラを覚えて頂かないと………と焦って、志葉家に入られて以降、これ以上はないというくらいに厳しく稽古を致しましたな。その甲斐あっての、殿の『火』のモヂカラ発現には、やはり黒子たちと祝いの宴を………」
「そう言えば、十臓との闘いを止めに来た時も、爺はそんなこと言っていた………か?」
長々と話を続けようとする彦馬を遮るように、丈瑠が呟く。
十臓との闘いの時は、いろいろな意味で切羽詰まっていたし、この一年間は、より大きな「火」のモヂカラを欲する毎日であったから、そういう意味なのだろうと、彦馬の言葉を気にはしなかった。しかし今改めて聞くと、彦馬は何か誤解をしているとしか、丈瑠には思えなかった。
一方で彦馬は、よもや全身全霊を懸けて育て上げた丈瑠を、自分が誤解しているなど露とも思わず、思い出話を続ける。
「そうです。爺はよく憶えておりますぞ。殿が初めて『火』のモヂカラをお使いになったのは、熱が下がってから稽古を再開した、その日でした。感動しましたぞ、爺は。殿はそれは憶えておいでではないですか?それは残念………」
彦馬がそこまで言った時、丈瑠が大げさなため息をついた。
「は?どうなさいましたかな?」
彦馬が丈瑠の顔を凝視する。それに、丈瑠が口を尖らせた。
「あのな!!『火』のモヂカラなら、俺は最初から使えたぞ」
彦馬が目を見開く。しばしの間、見つめ合う二人。やがて、彦馬が大きく手を振りかぶった。
「ああ。殿の仰られる最初が何時か、ですかな。いやいや、殿はお小さかったですからな。憶えていなくても仕方ありませんが、殿が最初に『火』のモヂカラを使われたのは………」
「だから!!」
丈瑠の言葉を全く信用していない彦馬に、丈瑠の声も大きくなる。
「『火』のモヂカラを使えるから、俺は志葉家に入ったんだ」
言い切る丈瑠に、彦馬が眉を寄せた。
「………はっ?」
丈瑠はもう一つため息をつくと、小さな声で呟いた。
「もしかしたら、父も知らなかったのかも知れないが………」
今まで、何とはなしに言うのが躊躇われて、誰にも言ったことがなかったこと。
「俺は………志葉家に入る直前にも、『火』のモヂカラを使えることを、多分、丹波だったんだろうが………確認されている」
「………は??何ですと!?」
彦馬には想像もつかなかったことのようだった。
「生まれて初めて使ったモヂカラが『火』だったんだ。不思議なものを見せられて、自分もやってみたくて………だから、よく憶えている。忘れようもない」
丈瑠の回想は、十七年前をさらに遡った。
小説 次話
2010.03.07