そんな風に考えながら、丈瑠を十八代目当主を担う者として育て続けた彦馬。そして丈瑠は、それら歴代の当主の限界すら次々と超えて見せた。それは、モヂカラによるものではなかったのかも知れない。しかし十七代目当主ですら倒せなかったドウコクを倒したのは、薫や丹波の援護があったにしろ、まぎれもなく丈瑠なのだ。丈瑠が率いる、丈瑠となら共に闘えると言ってくれたシンケンジャーたちなのだ。
「殿は志葉家当主として立派に育たれていた。そしてその殿が、殿だけのシンケンレッドになるために、そんな話をする必要はないと爺は考えたからです。前例も過去の経緯も、殿のシンケンレッドには必要ない」
彦馬がそう言いきれるほど、丈瑠のシンケンレッドは強かったし、勢いがあった。彦馬が丈瑠の養育係だからそう感じていたのではない。黒子たちもそう感じていた。
実際、前の当主にも仕えていた彦馬や黒子たちにしてみれば、ドウコクと闘い始めてからの十七代目当主率いるシンケンジャーと、丈瑠が率いるシンケンジャーでは、何もかもが違っているように見えたのだ。十七代目当主の時は、最終決戦の前からすでに諦めの空気が漂っていた。誰もが、あのドウコクに勝てるはずがないと心の底で感じていた。
しかし丈瑠がシンケンレッドになって以降の志葉屋敷には、丈瑠にモヂカラが足りなくても、勝てる策がみつからなくても、悲愴な雰囲気はなかった。丈瑠自身は考えるところも多く、悩みが深い毎日ではあったが、それでも丈瑠が当主であり、シンケンレッドで在った間は、ドウコクに負けると言う考えは出てこなかった。
シンケンジャーの四人の侍を招集した後は、その勢いはさらに波に乗る。次々に見つかり、志葉家に戻ってくる秘伝ディスクの数々。新たな電子モヂカラを持つ戦士の登場。新規折神の作成という、ここ数代では考えられないことから、封印されし牛折神の制御まで。果ては、歴代のシンケンジャーが完成できなかったインロウマルの完成。それによる悲願のスーパーシンケンジャーの誕生。さらに初代志葉烈堂より時空を超えて伝えられた、恐竜ディスクとハイパーシンケンジャー。新たな力が、丈瑠の率いるシンケンジャーにはみなぎっていた。例え封印の文字を使えなくても、これだけのことを成し遂げた丈瑠のどこが、歴代の志葉家当主より劣ると言えるのだろう。
そして、丈瑠が志葉屋敷を出た後だ。十七代目の最後の頃と同じような空気が、志葉屋敷に充満し始めたのは。
「実際のところ、殿をお育てしているうちに、爺は忘れてしまったというのもあります。そんなことは………」
「忘れた?こんな大事なことを!?馬鹿な!?」
彦馬の言葉を、ごまかしと受け取った丈瑠。しかし、彦馬は丈瑠に分かってほしいと思う。
「そのようなつまらない事実よりも、目の前の殿の事実の方が、爺には大切でした」
ここまで来ても、昔からの悪癖が抜けない丈瑠に、もう一皮剥けて欲しいと願っている。
「でも、俺は………!!」
それだけ言うと、丈瑠は俯いてしまった。真実の十九代目当主に就いた今でも、自分は本当の志葉家の当主ではないと、どこかで感じている丈瑠。丈瑠から、その想いを拭い去ることはできないのだろうか。
「爺は!!」
もしかしたら、丈瑠がそう思い続けても構わないのかもしれない。逃れられない辛い宿命を背負った志葉家の当主に、なりたくてなった訳ではないのだから。むしろ、志葉家などどうでもいいと丈瑠が思えれば、それでもいいのだ。しかし、丈瑠にはそういう考え方はできないだろう。幼い頃から、人を守るために、この世を守るために、志葉家の当主を背負い、強いシンケンレッドとして在れと………他の生き方があり得ないと思えるほど、丈瑠に刷り込んできたのは彦馬なのだから、それが痛いほど分かる。もう今更、丈瑠に他の生き方はできない。それは、丈瑠が志葉家当主という枠から解放されたときに取った行動からも、容易に想像できる。
それでは、どうしたらいいのか。彦馬は、ドウコクとの闘いが終わってから、ずっと考え続けていた。
彦馬は大きく息を吸う。思いもかけずに来た機会だが、今が、彦馬の想いを伝える時なのかも知れない。
「爺は、外道衆と闘う後世のシンケンジャーのために、今回のドウコクとの闘いのことも、克明に書き記してきております」
彦馬にとっては、当然のことだった。今回の闘いで、どれほど過去の文献や古文書が参考になったかを考えると、これを怠るわけにはいかないのだ。丈瑠もそれは知っている。
しかし、すぐに思ってしまうのだ。
「俺の………俺たちの闘いが………後世の参考になるのだろうか。封印もしなかった、ただ力づくなだけの闘いが………」
俯いたままの丈瑠の言葉に、彦馬の顔が曇る。彦馬や黒子、そしてシンケンジャーの侍たちからすれば、参考にならない訳がないと、言いたいだろう。封印するより完全に倒す方が、どれほど困難であるか。倒せないからの封印だったということすら、丈瑠には分かっていないのか。分かりたくないのか。それに丈瑠たちの闘いは、殆どが力づくではなかった。最後のドウコクとの闘いですら、丈瑠は幾度も闘い方をシミュレーションしていた。そして実際、古文書にある外道衆を、かなりの数、丈瑠たちはそれぞれの弱点を突いて、葬ってしまったのだ。
けれど丈瑠にしてみれば、正当でない血筋の自分がモヂカラとは違うかもしれない力で行った闘いを、志葉家の闘いの記録として残していいものなのか、と思わずにはいられないのだ。
「もちろん参考になるに決まっておりますぞ」
はぐれ外道である腑破十臓に指摘されたような、「いびつ」な丈瑠を作り上げてしまったのは彦馬だ。だから、こんなことを言う丈瑠から、どれほど目をそむけたくとも、彦馬は目をそむけてはいけないのだ。それは、丈瑠がシンケンジャーの前に跪いた時と同じだった。
「殿。その記録の最後。ドウコクとの闘いの結末として、爺は、初代から三百年経て、初代と同様のシンケンレッドが現れたと記しました」
俯いていた丈瑠が、ゆっくりと顔を上げた。彦馬と丈瑠は、暫し見つめ合う。やがて、丈瑠が口を開いた。
「………どういう意味だ」
訝しそうな顔で、探るように彦馬を見つめる丈瑠。それに、彦馬は微笑んだ。
「初代のシンケンレッドにも、シンケンレッドとしての連なる血筋などありませんでした。初代、志葉烈堂も、前例もなく過去の経緯もなく、もちろん親から受け継いだものでもなく、ただその人だけのシンケンレッドであったのです」
彦馬の言葉に、丈瑠が黒目がちの瞳を、瞬いた。
「殿と同じですな」
彦馬はそう言うと、丈瑠の瞳を覗き込んだ。丈瑠の瞳が、少しだけ明るくなったような気がした。
丈瑠は彦馬から眼をそらすように、庭に顔を向けた。暗い室内から外に目を向けると眩しくて、丈瑠は目を細める。
それと同じように、彦馬から告げられた言葉は、丈瑠には眩しかった。聞いて嬉しくもあったが、すぐに、自分はそんな良いものじゃない、と否定したくなる。そして、こんな風に自己否定することをこそ止めろと、彦馬が言っているのだということも判る。しかしそう簡単に、自分を変えられるものではない。
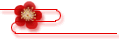
二人のいる部屋に、静かな時間が流れた。
「それにしても………」
丈瑠に話をした後、暫くの間、顎に手を当てて何かを考え込んでいた彦馬が、改めて首をひねった。
「殿の話を聞いていると、どうにも解せないことがあります」
丈瑠が庭から彦馬に視線を移すと、彦馬もじっと丈瑠を見つめた。
「志葉家に入られる前から『火』のモヂカラが使えたのであれば、殿は何故、あれほど爺が厳しく稽古をしている間に、『火』のモヂカラを出されなかったのですか?殿は毎日泣きながら稽古をされておられたのに………そこが、どうにも腑に落ちませんな」
彦馬のまっすぐな追及に、丈瑠の顔色がさっと変わった。
「それは………」
そう言ったきり、黙ってしまう丈瑠。
「何ですかな?」
丈瑠をずっと育ててきた彦馬には、あまりにも分かりやすい丈瑠の反応だった。わざとらしくも重ねて尋ねる彦馬に、丈瑠が顔を背けた。
「爺が悪いんだ」
そう小さい声で呟いて、俯く丈瑠。何が起きても、絶対に人のせいにしたりしない丈瑠だが、唯一、彦馬にだけはこんな口をきく。もちろん彦馬には、それが本気ではないことが分かっている。
「はあ?爺が悪いと?」
だから、意地悪くも彦馬は丈瑠の顔を覗き込む。
「それは、どのように?」
丈瑠が唇を噛みながら、さらに顔を背けた。
「俺は……あれが……モヂカラだなんて知らなかったから………」
「………は?」
ぼそぼそと呟く丈瑠の言葉は、彦馬には理解できなかった。
「何ですかな、殿。もっと判り易く」
「だから………」
そこまで言った丈瑠は、覚悟を決めたのか、彦馬の方を振り返った。
「爺に要求されている、半紙に筆で書くことによって発現する『モヂカラ』と、あのよくわからないけれど、俺が強く思うことで何かが出てくる行為が同じだって、俺には分かってなかった」
少しだけ、不貞腐れたように話す丈瑠。
「………筆で書くのとモヂカラが結びついていなかった………と?」
彦馬が眉を寄せると、丈瑠の唇が尖った。
「だって俺が最初にモヂカラを使った時は、俺は『字』なんて知らなかったんだ。だからそのモヂカラと、爺が言う字を書いて使う『モヂカラ』が結びつく訳ないだろう!?」
きっとあの頃の丈瑠が、言いたかったことなのだろう。彦馬は、あれほど過酷な訓練を丈瑠に強いていたが、その訓練自体が、そもそも何のためにしているのか、何をしようとしているのか、幼い丈瑠には分かっていなかったのだ。確かにあの頃、すでに志葉家は臨戦状態だった。当主も家臣も、モヂカラを使える者は誰一人として、丈瑠に実際のモヂカラを教示する余裕はなかった。
彦馬の顔が曇る。丈瑠の今更ながらの告白に、心が痛い彦馬だった。しかし丈瑠はそれに気付かずに、続ける。
「それに爺は、モヂカラで大きくて熱い炎を出す、みたいなことをずっと言っていた」
「そうでしたな。早く殿に、大きな『火』を覚えていただきたくて」
彦馬が自分の痛みを心の奥に押し込んで応えると、丈瑠が子供の頃のような顔をした。
「それって………怖かった」
「………」
彦馬の胸が再び、痛む。その顔はまさしく、『モヂカラ』の稽古中に、彦馬が言うことを黙って聞いていた幼い丈瑠の表情だったから。
「そんな炎が出たら、火傷しそうだし、火事になるんじゃないか………って、ずっと思っていて」
小さかった丈瑠には、彦馬の言っていることが本当に理解できなかったのだ。小さくても、『火』や『炎』が怖くて熱いこと。大きな火が、家の中で発生すれば、火事になることくらいは、想像がついた。だから、ますます困惑した。彦馬の要求に。どうしていいか、わからなかった。言われるたびに泣きたくなった。
あまりのことに言葉もなく聞いていた彦馬に、丈瑠が最後の答えをくれた。
「だけどドウコクと先代の闘いの時、表屋敷の方からもの凄いモヂカラが発せられていたのを、俺は奥屋敷で感じたくないのに、感じ取ってしまった」
はるか遠い時の果てのことを、思い出すように、丈瑠はぽつりぽつりと語る。
「ものすごく怖かったけれど、その時初めて判ったんだ。ずっと爺が言っていた『大きくて熱い炎』、筆で書いて発現する『モヂカラ』、それと俺の持っている『力』が、やっと俺の身体の中で結びついた」
だから丈瑠は、十七代目当主とドウコクの最終決戦の後、体調が戻り稽古を再開したその日に、『火』のモヂカラを使えるようになった、と彦馬には見えたのだ。
もしかしたら十七年前の闘いの後、丈瑠が長く熱に意識をなくしていたのも、この『全てが結びついた』ことを、丈瑠が自らの心身で消化吸収するために必要な時間だったのだろうか。
「そうでしたか」
彦馬は深い溜息と共に頷いた。
十七年前の悲惨な闘い。あの闘いの中で、丈瑠は十七代目当主が手放した獅子折神を受け取り、志葉家十八代目当主を担うシンケンレッドとしての道を歩み始めた。まさしく時を同じくして、丈瑠の中で本格的な『モヂカラ』の始動も生じたということなのだろう。
「獅子折神を通じて、殿は先代の殿から『火』のモヂカラ、つまりはシンケンレッドを受け継がれた………のですかな」
彦馬の言葉に、丈瑠が驚いたように顔を上げた。
「初代烈堂と同じように、親から受け継いだのではない、殿の『シンケンレッド』ではありますが、先代のシンケンレッドの『なんとしても、この世を守る』という思いは、獅子折神を通じて殿にも伝わったのでしょう。先代の殿が亡くなる時にその思いを託せる事ができた、シンケンレッドを継げる可能性のある者は、殿しかおられなかったのですから………」
小説 次話
2010.03.20