丈瑠は彦馬の言葉に、胸の奥を突かれた。丈瑠は再び、庭に視線を飛ばしつつ思案する。先ほどから、気になっていたことがひとつあったのだ。それが、彦馬の最後の言葉により、ますます気になってきた。
丈瑠は庭を向いたまま、ある事実を繰り返して確認した。
「俺が三歳の時、俺にモヂカラを披露してくれたのは、志葉家十七代目当主だった………のだな」
丈瑠はずっと勘違いをしていたが、十九年もの年月を経て明らかになった事実。あの時、モヂカラを興味引かれるモノとして間近に見なければ、丈瑠のモヂカラの発現はあり得なかった。不思議なめぐり合わせに、彦馬も感慨深く頷いた。
「ドウコクとのことで忙しそうだったし………俺は同じこの屋敷にはいたが、十七代目当主とはまともに顔を合わせたこともなかった。だから先代は、俺のことなど、ろくに知りもしないのだろうと思っていた」
丈瑠は、十七代目当主は、丈瑠のことを何とも思っていないと考えていた。ただの表向きの存在。いつかは、正当な当主にとって代わられる一時的な飾り物。彦馬にそうは言われなくても、勝手にそう思い続けていた。しかしあの時、丈瑠にモヂカラを披露してくれたのが、十七代目当主だとなれば、丈瑠の印象は全く変わる。それはつまり、十七代目当主が丈瑠に興味があったということ。丈瑠は十七代目当主に選ばれたのだということ。
「確かに、殿が志葉家に来られたころには、もう闘いが佳境でしたからな。先代が殿を気にかけている余裕はありませんでした。しかし、まさしく先代が、殿を選ばれたということに変わりはない。そして丹波殿にそのことを伝えられたのでしょうな」
丈瑠あってこその、対ドウコク、一世一代の策だったのだ。そしてその策自体は失敗に終わったが、ドウコクを倒すと言う意味では成功に終わった。丈瑠が、全ての鍵だったのだ。
手塩にかけて育ててきた丈瑠のモヂカラの才能が、十七代目当主が認めるほどのものであったことを彦馬は今更ながら嬉しく思った。
「初代と殿だけが、血筋など受け継がなくとも、『火』のモヂカラを持ちえたのです。そして、それを十七代目当主も知っておられた」
そう考えると、今、丈瑠がここに十九代目当主として在るのも、その頃からの定められた運命だったのではないかとすら思えてくる。
十七代目当主は感じていたのではないだろうか。丈瑠の中にあるものを………
「………でも」
そこで丈瑠の声が微妙に揺れた。
「さっき爺が言っていたが………モヂカラって、人に見せてはいけなかった………っけ?」
歯切れの悪い丈瑠の言葉。
「は?何ですと?」
丈瑠の暗い表情ではなく、ばつの悪そうな顔を見て、彦馬は何かあることを直観する。
「俺も………見せたことあるぞ。前に俺一人でいる時、泣いてる子がいたのであやそうと思って………」
丈瑠が彦馬にぐるりと背中を向けて、再び布団に横になる。都合の悪いことがあるとすぐに背中を向けて視界から消したがる、丈瑠の悪い癖だった。それを見ると、彦馬の声も思わず大きくなる。
「はああ?」
条件反射だ。
「それは、まさか家出されていた時のことですか!?モヂカラで子供をあやした〜?」
丈瑠が布団を頭の上まで引き上げながら、小さな声を出した。
「………い、いけなかったのか?そんなこと習ったことない」
「習わなくとも、常識ですぞ!!!見られてしまうのは仕方ないとしても、わざわざ見せるものではありません!!例え、殿が家出中で心細くても、常識は変わりません!!そんなことで、子供に慰めてもらおうなどと」
思わず、布団脇の畳を叩いてしまう彦馬。丈瑠が布団の中で首をすくめながら叫んだ。
「こ!心細かった訳じゃないし、慰めてもらおうとも思ってない!!モヂカラ自体が常識じゃ計れないのに、そんな常識あるか!!」
「まあ、でも………」
亀のように布団の潜り込んだまま出てくる気配もない丈瑠に、彦馬も話し向きを変えるしかなかった。
「それで殿が十九代目当主として先代の悲願だったドウコクを倒すことに成功し、今ここに居られるのです。先代のなさったことは、正しかったのでしょう」
彦馬が仲直りのつもりで言った言葉に、丈瑠の布団がぴくりと動く。
「じゃあ、俺がモヂカラを子供に見せたのは?」
布団の中から聞こえてくるくぐもった声に、彦馬はため息をついた。
「それは、殿が迂闊だったと言うこと以外、ありませんな」
布団の中で丈瑠が不貞腐れているのが、彦馬には見えるようだった。
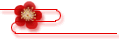
「しかし多分、先代の殿が闘いに悩み始めた頃でしょうな。殿と出会われたのは」
いつまでたっても、布団から顔を出さない丈瑠。もしかしたら、彦馬の当初の希望通りに寝てしまったのだろうか。それでもいいと思いながら、彦馬は独り言のように呟いた。
「今のうちに早く後継ぎを………と周囲も先代も焦っておられた。だから、七五三で武者姿をしている幼い殿に何か感じるものがあったのでしょうな」
十七代目当主の時代、ドウコクとの闘いは長いものだった。終わらない闘いに、悩みを深めていた十七代目当主。
勝てないかもしれない。
負けるかもしれない。
そういう思いは、既に十七代目当主の中に芽生え始めていて、精神的に追いつめられて行ったに違いない。このままでは負けなくとも勝てはしない。そうすると、志葉家の次代に解決を先送りにするしか方法はない。けれどその次代が、後継ぎがまだいない。それでは志葉家は滅亡し、この世界も滅亡してしまう。
あの頃の当主の悩みは、志葉家家臣全員の悩みでもあったのだ。
そんな追いつめられた当主の前に、突然現れたモヂカラの才能を持つ丈瑠。
もう丈瑠の中にそういうものは残っていないのかもしれないが、丈瑠本来のモヂカラは、志葉家の破壊的なモヂカラとはずいぶんと異質なものだった。丈瑠が志葉家にきたばかりの頃、丈瑠が彦馬に見せたモヂカラは、きれいで、夢にあふれたモヂカラだった。暗い志葉屋敷の中が、そこだけふんわり明るくなるようなモヂカラだった。彦馬は、そんなモヂカラがあることを、その時初めて知ったのだ。シンケンレッドとなった丈瑠が、もうそのモヂカラを見せることはない。それでも、今でもあのモヂカラが丈瑠の本質であり、丈瑠の強さの源だったのではないかと、彦馬には思えてならない。
十七代目当主も彦馬と同様に、丈瑠の志葉家とは異なるモヂカラを知っており、それがドウコクを倒す力になるかも知れないことを、感じていたのではないだろうか。志葉家の血をひかない丈瑠のモヂカラの中にこそ、むしろ志葉家の未来を見たのではないだろうか。
今更考えても仕方のないことではあったが、彦馬はそのような気がしてならなかった。
そして考えているうちに、やがて彦馬も、眠りの底へと引きずり込まれていった。
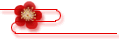
ぴちょん
ぴちょん
彦馬の耳元で、音がした。
ぴちょん
ぴちょん
彦馬がうっすらと目を開けると、部屋は薄暗かった。はっとして起き上がる彦馬。腰の痛みは既にない。それでも念のために腰に手を当てつつ、傍らの丈瑠の寝ている布団に目をやる………つもりが、そこには布団がなかった。ぎょっとする彦馬。
「殿!?」
寝ても覚めても丈瑠第一の彦馬らしく、起きるや否や考えるのは丈瑠のことだ。
「と、殿〜!?」
彦馬は布団を跳ね除けると、閉まっている障子を開ける。しかし入ってきた光の突き刺すような眩しさに、思わず手で目を覆った。目の前が、陽の光に真っ白になっていた。暫し彦馬は絶句する。
一面の雪景色。しかし空は晴れ渡り、陽の光がさんさんと雪の上に降り注いている。
昨日から一晩が過ぎていた。丈瑠と床に入ったのが夕方なので、夕食も取らずに寝ていたことになる。いくら腰が痛いと言えども、これは寝過した!!彦馬はそう思う。時計を見れば、それでもまだ八時だった。
ぴちょん
先ほど夢うつつの中で聞いた音。彦馬が音のした方向を見ると、庭木の枝に積もった雪が陽の光に溶け出して、雫となって落ちて行った。それが庭石の窪みに水たまりを作り、そこで音を出していた。
ぴちょん
彦馬は冷たい空気を胸一杯に吸い込んだ。それはとても清々しく、気持ちの良いものだった。
「昨日はやけに寒いと思っておったら、やはり雪になったのか。しかし今朝はもう、こんなに天気も良く………春も近いのお」
そこまで呑気に一人呟いて、再び彦馬ははたと思い出す。自分が探していたものを。彦馬は両手を打つと、途端に現実に戻り、廊下を踏みならしながら、表屋敷の方向へと歩みだした。
いつも丈瑠が朝食を摂る部屋に行くと、そこには丈瑠の膳が用意されていた。しかし丈瑠はまだいない。食事係の黒子が、驚いたように彦馬を見上げた。丈瑠の膳には、汁物も飯も盛られていなかった。丈瑠が膳についてから、それらは給されるのだろう。ということは、予定通りの食事の支度と言うことだ。
しかし朝八時と言えば、志葉家の通常のスケジュールではとっくに丈瑠の朝食は終わっているはずだった。朝稽古が長引いた場合は別だが、シンケンジャーの侍たちがそれぞれの場所へ帰って行った今、わざわざ通常のスケジュールを崩してまで、丈瑠一人が朝稽古を長引かせることはない。さらに稽古をする場所だが、通常は庭で行う。もちろん志葉家には道場もあり、丈瑠の剣がまだ拙い頃はそこでの稽古も行っていたが、外道衆に道場剣法は通用しないので、今はもう使っていなかった。そうすると、この雪である。稽古で朝食が遅れている訳ではなさそうだった。それでは何があって、規則正しいことを旨とする志葉家の朝食が遅れているのか。
彦馬は顔をしかめながら、屋敷の中を歩いていく。するとふいに、彦馬の鼻を何かがくすぐった。
「!?」
嫌な予感が彦馬の胸に押し寄せる。彦馬が次の間に進もうとするところで、黒子に何か指示を与えながら、丈瑠が長い廊下の向こうからやってくるのが見えた。
「殿!!」
彦馬が叫ぶと、丈瑠はぎょっとしたような顔で彦馬を一瞬見たが、すぐに普通の顔に戻った。黒子が丈瑠の前に来て、丈瑠のネルシャツの襟元を直す。それに頷くと丈瑠はそのまま、食事の間に向かった。彦馬のすぐ横に来ても、丈瑠は何も言わなかった。彦馬は丈瑠の顔を探るように見てから、深々とお辞儀をする。
「殿、おはようございます」
「ああ」
それに、さも何気ないように応える丈瑠。そして丈瑠は彦馬をすっと通り過ぎた。彦馬は丈瑠が通り過ぎた後、鼻をこする。そして廊下に立ったまま腕組みをして、食事の間に入り朝食の膳につく丈瑠を眺めた。丈瑠はあくまで何気ない顔で、膳に向って一礼すると、朝食を食べ始めた。それを彦馬は、廊下でじっと見つめ続ける。
丈瑠はあまり食が進まないようだった。とりあえず全ての皿に手をつけ、汁椀を置いたところで、丈瑠は大きく息をついた。それまで真っ直ぐに前を向いていた丈瑠が、彦馬のいる廊下に視線を向け、彦馬を睨んだ。
「何だ?爺。何か言いたいなら、言え!!」
丈瑠は箸も膳に置く。それを見た彦馬は、食事の間に入り丈瑠の前に正座した。
「腰はもういいのか?」
彦馬の動作を、丈瑠が心配そうに見つめる。しかし彦馬はそれに応えず、丈瑠の膳のすぐ前から丈瑠をじっとみつめる。やがて丈瑠は堪らなくなって、彦馬から眼を逸らした。
いつもこうやって意地比べで負けている………とでも思ったか、俯いた丈瑠の手が口元に行き、彦馬から注意が逸れる。その瞬間だった。
「殿!!」
彦馬は言うが早いか、丈瑠の胸元に手を伸ばした。気付いて、彦馬を避けようと後ずさる丈瑠だったが、遅かった。
「これは、何ですかな!?」
そう言って、彦馬は丈瑠が上着として着ているネルの上着を引き剥がした。その下には、いつも着ているTシャツはなく素肌だった。そしてそこには血濡れた包帯が斜めに幾本も走っていた。先ほどから廊下に漂っていたのは、この怪我の手当てに使用された消毒液の匂いだろう。
「な、何って………」
睨む彦馬から、座ったまま後ずさった丈瑠は、彦馬が横に置いたネルシャツに手を伸ばした。
「何ですかな?」
痛そうにしながらも、シャツを羽織り直し、胸元を合わせる丈瑠。既に見られてしまったものを、今更隠してもと思う彦馬は、腕を組んで睨んだままだ。そんな二人を、給仕の黒子と世話係の黒子が、おろおろしながら見つめていた。
「殿!これは、何なのですか!?」
「何………えっと………何だろう?」
シャツを着終わり手持無沙汰になった丈瑠が、再び問われて、困ったように呟く。世間ずれしていない丈瑠には、こういう時に適当なことを言う知恵もない。せいぜいが笑って誤魔化すことくらいしか知らないのだ。
「はは………」
丈瑠の虚しい笑顔にも、彦馬は睨んだ顔を崩さなかった。彦馬は腕を組みなおしながら、丈瑠から部屋の隅にいる黒子に目をやった。
「雪に滑って転びでもされましたか」
彦馬がいかにも適当なことを言う。それは実は、黒子への嫌味でもあったのだが、丈瑠は気付かない。むしろ丈瑠は嬉しそうな顔をした。
「あ、ああ、そう。そうなんだ。朝稽古をしていて、雪に足を取られて………」
丈瑠の反応の拙さに、半分呆れながら、彦馬はため息をついた。
「それで刀で切られましたか」
「そう。そうなんだ。ちょっとさくっと………」
「外道衆にね」
丈瑠は大きく頷いた。そして、再びぎょっとした顔になる。
「殿!?何故、爺を起こされなかったのですか!?爺はシンケンジャーの侍たちがいない今、殿の闘いを見届ける義務があるのですぞ!?」
丈瑠はがっくりと肩を下げて、俯くしかなかった。
小説 次話
2010.03.27