食事の間から奥屋敷に場所を移して、改めて丈瑠は彦馬に説教をされる。
「だから!!」
しかし丈瑠も抗議せずにはいられない。
「爺は腰が痛かったんだし、雪はかなり降って来て冷えこんでくるし、真っ暗だし………」
そこで彦馬がさらに眉を寄せた。
「暗い………そんな時間から、ですか!?まさか昨晩からとは言われませんでしょうな!!ずっと雪の中におられたんですか!?」
いつも彦馬は、丈瑠の言いたくないことを言い当ててしまう。丈瑠は口をとがらせながら言い訳した。
「隙間センサーで行った場所では、外道衆がすぐに見つからなかったんだ。だから、その周囲を探していたら夜が明けてしまって………」
確かに時間が掛かった。闘いにではなく、探索に、だ。深夜、凍えるような雪の中を、外道衆を探して歩きまわるのは、丈瑠にとっても楽なものではなかった。今から考えても、腰が痛い彦馬に気付かれずに行けて良かったと丈瑠は思った。だから、どんなに彦馬に説教されようと、丈瑠は同じ状況なら、同じことを、今後もすると思う。
だから、断じて彦馬に謝らないと唇を噛んでいる丈瑠を見て、彦馬も諦めたようだった。
「わかりました」
彦馬は正座したまま目を瞑った。
「今回だけは、殿の判断を良しとしましょう。爺が付いて行っても足手まといだったということで」
「え!?」
しかしそう言われると、また辛い丈瑠だった。
「そんなことは言っていない!!ただ今回は寒いし、爺の腰の具合が良くなかったから!!」
必死で言い訳する丈瑠に、彦馬の顔も緩んだ。実際、昨晩、丈瑠たちの出陣に気付いても、付いて行けたかどうかは、怪しいのだ。
「もう良いです。さて、ところで相手はどんなアヤカシでしたかな?それともナナシだけ?」
これも彦馬が気になって仕方ない所だった。だからこそ、丈瑠について行き、確認したかったのだ。外道衆の大将であるドウコクを倒した今、三途の川の水は激減して、外道衆の勢いは弱まっているはず。それでも、ちょろちょろとナナシがこの世に出てくるのは昔からのことだが、丈瑠が怪我をするほどの相手となると、疑問が残る。
何年も前の丈瑠ならいざ知らず、今の丈瑠がどれほど強いか。一年前ですら、ナナシなど100匹相手しても、丈瑠が怪我を負うことなどあり得ないはずなのだ。
さすがに丈瑠もそう思っていたのだろう。それもあって丈瑠は口が重いのだ。丈瑠は視線を落とした。
「それが………ナナシには見えなかった………」
凍える中でやっとみつけた、一体だけの外道衆。初めはナナシだろうと高をくくって近づいたそれは、どうにも見た事がない外道衆だった。
「………見えなかった?」
「………ナナシじゃなかった。結構、強かった」
そう言ったところで、横から黒子が写真を差し出した。それは黒子が情報収集用に撮影した今回の外道衆の写真だった。彦馬はそれを受け取り、じっくりと見つめる。丈瑠もその写真を覗き込んだ。
「これは………」
彦馬が呟く。
「見たことがありますな………ドウコクの縛りが無くなった時に出てくるアヤカシもいますから」
「え?三途の川の水が少なくなってもなのか?」
丈瑠が目をまんまるにして聞き返した。
「確かに三途の川の水の増減は、外道衆の勢力の大きな目安です。しかし、それだけでもない。ドウコク亡き後、外道衆がどの程度になるか………爺もいろいろ研究を重ねていたのですが………」
そう言って彦馬が、自分の部屋から黒子に持って来させたのは、一冊の和綴じ本だった。
「それは?」
丈瑠が意外そうな声を出して、彦馬の手元を覗き込む。何故ならその本は、いつも丈瑠や彦馬たちが参考にしている古文書とは違い、それほど古いものには見えなかったからだ。
「十七代目当主がドウコクを封印した直後の、外道衆の動向を記したものです」
「それって、まさか………」
彦馬が丈瑠に頷く。
「そうです。小さかった殿をお守りしながら、爺と黒子で記録してきたものです。後世には、このような記録も大事なのです」
そう言って、彦馬はその本のページを繰った。繰りながら彦馬の胸に、感慨深いものが込み上げてくる。
「しかし、まさかこんなに早く、この本を自分で使用することになるとは、思いませんでしたな。嬉しい誤算ではありますが」
この本を記録していた時は、こんなに早く「ドウコクを倒した後」という未来がやってくるとは思ってもいなかった。
しかし、もしかしたら予感はあったのかも知れない。それとも、そうあって欲しいとの希望か?だからこそ、克明に記録したのか、自分は。しかし、予感にしろ、希望にしろ、十七代目当主が闘っている時には描けなかったものだ。彦馬が丈瑠を育てていたからこそ、感じた予感であり持てた希望なのだ。
彦馬は一人想いを馳せながら、目指すページを探した。
「ああ、あった。殿、ここです」
彦馬がそう言って指した先には、確かに先ほど丈瑠が始末してきたアヤカシが載っていた。
「十七年前に出てきた時は、爺と黒子では追い払うのが精いっぱいでしたが、前の時もこやつは、ドウコク封印後にすぐ出てきておりますな」
彦馬が顎の下に、手を当てて考える。
「外道衆が生まれるのは、三途の川の勢力。この世に出てくるナナシの数で、外道衆の勢力を計っていたのはそのためです。その勢力はドウコクのようなアヤカシが勢いを増すことで増える。出てくるナナシの数が増えれば、外道衆の大将が生まれたり復活する前兆と言うことなのです」
丈瑠は頷く。今までにも何回も聞かされた、丈瑠にとっては外道衆に関する常識だった。そんな丈瑠を見つめながら、彦馬はさらに続ける。
「しかし一方で、ドウコクは一部のアヤカシの動きを封じ込めて統制していた、という事実もあります。ドウコクの縛りが無くなると………」
丈瑠は再び頷いた。
「夏に外道衆が暴走したが、あれがドウコクの縛りが解けていた頃、ということか」
今度は彦馬がそれに頷いた。
「それもあって、爺は、新たな力としてインロウマルを用意すべきと言ったんだな………」
「そうです。そして殿が毒を飲まされたのも、誘拐されたのも、同じ頃。あちこちで外道衆がやり放題と言う、あの状態です」
丈瑠が目を瞬いた。
「じゃあ………今はそれと同じってことなのか!?」
丈瑠が拳を握りしめる。
「それって………」
丈瑠の喉がごくりと鳴った。
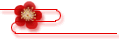
かつて。
昨年のいつごろだろう。
丈瑠は彦馬に言ったことがある。
「俺は弱くなったのか」
そんなことを呟くこと自体が弱くなった証拠。そんな風に思っていたはずなのに。
一人で全てを背負っていくことが普通で、それに対して何の感情もなかったはずなのに。いや、どんな感情も湧かないように、自分の心を殺して生きてきたのに。そうやって必死に自分を奮い立たせて闘いに臨んでいたのに。
シンケンジャーの侍たちと共に闘うのが普通になったら、丈瑠の心のどこかで何かが生まれた。
「たまには弱い殿さまだっていいじゃない」
そんな風に言う茉子の言葉に、反発を覚えながらも、安心していた。丈瑠を想い、仲間として支えようとしてくれる侍たちの気持ちは、丈瑠を弱くした。彦馬はそうは思っていなかったが、丈瑠にはそう思えた。
「あの状態がこれから続く………」
今の自分の実力から考えれば、一人でもなんとかなるだろうに。むしろ一年前の状態より、ずっと楽なはずなのに。それでも一人で闘っていくのかと思うと、心の奥底のどこかが痛む。それがこんな情けない台詞を自分に吐かせている。分かっていても呟いてしまう丈瑠に、彦馬が首を振った。
「違いますぞ、殿」
丈瑠が顔を上げると、彦馬は見ていた本を閉じた。
「ドウコクの勢力が大きかった時に、生み出された外道衆は、そのまま残ります。しかし力は時間と共に弱くなっていく。自らを生み出したエネルギーが枯渇して行くからです」
彦馬の言葉に聞き入っているのは丈瑠だけではなかった。部屋の隅やそこかしこに控える黒子たちも、固唾をのんで彦馬の話を聞いていた。
「つまり、ここ暫くは、強いアヤカシも出てきましょうが、ナナシの数は激減でしょうし、時と共に強かったアヤカシも弱体化します。そして、新しいアヤカシは今の三途の川の状況では、生まれません」
彦馬の話に、その場の空気が緩んだ。
昨晩から探し回り、闘いで一応は倒してきたアヤカシ。
ドウコクを倒したにも関わらず、あのようなアヤカシが今後も出てくるのか。それを丈瑠一人で相手して行かねばならないのか。それでは、かつてのように志葉家も臨戦状態を保たねば!!そう気負っていた空気が解けた瞬間だった。
「このような闘いが続くのも、あと暫くの間です。きっと残るは僅かなアヤカシのみ。それさえ倒せば、後はたまに出てくるナナシのみ。暫くは静かな日々を過ごせましょう。もちろんその時々、波がありましょうが」
そこまで彦馬が話した時、丈瑠がふわっと笑った。
「そっか」
彦馬と二人だけの時ならいざ知らず、丈瑠が屋敷内で黒子が何人も控えている場で、こんな風に笑うことは珍しい。彦馬が目を見開いていると、丈瑠の身体が彦馬に寄ってくる。
「良かった………」
このような弱気とも取れる発言も、黒子の前でしたことはない。彦馬が顔をしかめていると同時に、丈瑠の身体が彦馬の胸に倒れこんできた。
「と………」
殿!?と言おうとした彦馬は、抱きとめた丈瑠の身体の熱さに気付く。すぐに丈瑠の額に手をやった彦馬は、その高熱に驚いた。
「殿!?何ですか?この熱は!?」
彦馬が叫ぶが、既に腕の中の丈瑠は意識を失っていた。と同時に、黒子が彦馬と丈瑠に走り寄ってくる。
「ああっ!!」
彦馬が悔しそうに膝を叩いた。
「考えてみれば、殿はここ数日、たちの悪いお風邪を召されていて………」
それから、言っても仕方ないとは思いつつ、黒子を睨んで呟いてみる。
「それなのに、昨晩から雪の中で徹夜の捜索………その上、アヤカシと戦闘、さらには刀傷とは!!そりゃあ熱もでましょうぞ!!」
言いつつも彦馬は、その広い胸にしっかりと丈瑠を抱きしめた。
どんな時でも。
自分がどんなに辛くても。
いつでも、この世を守ること、人々を守ることを、自分のことより優先してきた丈瑠。
そう教え込んだのは彦馬だったが、ここまで素直にそれを守る丈瑠を見ていると、少しだけ哀しく感じてしまうこともある。
それでも。
誰よりも。歴代のどの当主よりも、彦馬にとっては、強くて立派な志葉家当主。そしてシンケンレッド。
それが彦馬の、彦馬が育てた、志葉丈瑠なのだ。
彦馬にとって、何よりも大事な宝物なのだ。
小説 次話
2010.04.03