昨日と同様に障子が開け放たれた、丈瑠の寝室。そこで眠る丈瑠の横に、彦馬が控える。
寝ている丈瑠の顔は、ドウコクを倒した強いシンケンレッドと同一人物とは思えないほどにあどけなかった。額に掛かる一筋の髪を、脇に戻しながら、彦馬はまたも胸の内に湧き上がってくる想いに顔を曇らせた。
ドウコクを倒して以来、何度も何度も考えずにはいられないこと。丈瑠が無事だった嬉しさと共に、深い後悔に悩まされる毎日だ。彦馬は、丈瑠の顔をじっと見つめた。
あの小さかった殿が、こんなに立派になられて、血祭ドウコクまで倒された。
でも、それはきっと、本来の殿のお姿ではないのでしょうな。
もう一度、あの小さかった殿を、この手でお育て出来たら。
あの時にはできなかったこと。してはならぬと勝手に思い込んでいたことも、してあげられるのに。
もっと自由に、もっと豊かに生きることを、殿にお教えすることもできたかも知れないのに。
けれどそれは、過ぎたから言えること。ドウコクを倒せたという結末が分かった今だから、思えること。そうは分かっていても、思わずにはいられない。
彦馬は自分の娘の時は、世の父親の多くがそうであるように、仕事が忙しくて育児には関われなかった。ドウコクとの闘いのこともあり彦馬は家を空けることも多く、彦馬の妻はきっと苦労したことだろう。しかし愚痴一つこぼさなかった彦馬の妻のお陰で、彦馬の娘は立派に育ち一人立ちした。そして彦馬が妻にろくに報えぬうちに、妻は逝ってしまった。
時を同じくして、彦馬に巡って来た丈瑠の養育係という重役。それが仕事でもあったし、この世の中の存亡と関わっていたこともあって、彦馬は、真実、全身全霊を込めて丈瑠を世話し育て上げた。けれど、どこかに妻への思いも重なっていたことは否めない。在りし日の妻への償いも含めて、彦馬は丈瑠の養育に心血を注いだ。
そうして彦馬は、様々なことを知る。幼い子供を抱くと甘いにおいがすること。自分の膝の上でおもらしをされても嫌な気持ちにならないこと。幼い子供を慈しむ気持ちの全ては、自分の娘ではなく、むしろ丈瑠によって知らされた。
だから本当は、もっともっと丈瑠を可愛がってあげたかった。優しくしてあげたかった。どんな豪邸に住み、多くの家臣に囲まれていても、丈瑠は親を亡くした子に違いはなかったのだから。
けれど、どうなるかわからない未来を見つめながら育てている間は。そのどうなるかわからない未来を変えることができるのは、丈瑠しかいないと思っていた間は。丈瑠を甘やかすことはできなかった。ただ強く、ひたすら強く、決して負けないように。そう教え込むしかなかった。それだけが、丈瑠の存在意義であるかのように。
常識的な教育から言えば、激しく外れていることを彦馬は丈瑠に刷り込み続けたのだ。丈瑠は、彦馬が望んだとおりに育った。けれどまた、そこまで刷り込み続けたのに、丈瑠にはそれとは違う価値観もどこかで育てていた。だからこそ、丈瑠は悩みが深かった。
こんなに早く、闘いから解放される日が来ると判っていたのならば、もっと違う教育のしようもあった。
志葉家当主から解放された丈瑠の取った行動を見た時。そしてドウコクとの闘いの勝利の後からずっと、彦馬の頭を離れないことだ。しかし彦馬には、もうひとつの真実も見えている。もし、ここまで厳しく丈瑠を育てていなかったら、そもそも十臓にもドウコクに勝てたかはわからない。いや、勝てなかっただろう。そうだとすれば、今ここに、丈瑠が生きていることもないのだ。だから、ドウコクを倒した後のことを考えた教育などはできなかった。
そうやって突き詰めて行くと、丈瑠を志葉家当主として育てることが決まった時の、丈瑠の想定人生が見えてきてしまう。つまりは、十七代目当主と同様のことを想定していたのだ。あの頃、薫が封印の文字を覚えて出てくることは想定していなかった。すると丈瑠の役目、人生とは、ドウコクに命からがらダメージを与えて、次代当主が育つまでの間の時間稼ぎをする。あるいは、ドウコクと闘い続け、闘い続け、そして勝てない闘いの中で、死んでいくことを想定されていたのだ。闘いが終わった後の丈瑠の人生など、ないものとされていたのだ。
誰もがこれを判っていて、でも考えないふりをして、幼い丈瑠にそのような人生を押し付けた。彦馬も酷い話だと思いつつ、この策の成功のために、この策に相応しい丈瑠を造り上げようとした。
ただ、育てて行くうちに、彦馬の気持ちもそれだけではいられなくなっていった。それでもこの世を守るためには、十七代目当主の大方針は変えようもなく、丈瑠を闘うだけの存在へと育てて行くしかなかったのだ。
だから彦馬は、ドウコクとの闘いが終焉した時に、決心をしたのだ。
これから先は、本当に丈瑠のために生きよう。志葉家のためでもなく、世の中のためでもなく、ただ丈瑠のためだけに、丈瑠の未来のためだけに生きようと。それが、丈瑠をこんなふうな人間に………外道の十臓にすら「いびつだ」と評されてしまうような人間にしてしまった自分の責任なのだから。
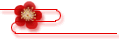
「人間、暇になると、昔のことばかり考えてしまいますな」
彦馬が一人ごちる。
「爺は、この頃、殿が見せてくれた初めてのモヂカラをよく思い出してしまうのです」
彦馬は腕を組んで、天井を見上げた。すると、否が応にも浮かんできてしまう光景。
志葉家に入ったばかりの頃。丈瑠が「火」のモヂカラを使えないと、彦馬が信じていた頃のことだ。
志葉の屋敷の薄暗い雰囲気が怖くて、いつも自分の部屋に光るシャボン玉のようなものを出してしまう丈瑠。それは明るさを補いもしたが、むしろメルヘンチックな雰囲気を醸し出してしまい、あまりにも志葉家には不釣り合いだった。しかし、それが人の心を和ませたのは事実だ。その訳のわからないものが漂う中で、彦馬は幾度、丈瑠に絵本を読んでやったことだろうか。
それだけではない。思い起こせば、他にもいろいろなことがあった。
彦馬の眼には、それら全てがモヂカラというよりは魔法に見えた。確かにモヂカラ自体が魔法のようなものではあったが、彦馬の知るモヂカラは闘いの時に使うものだったし、そのようなモヂカラしか知らなかったから、最初は丈瑠がそれをしていることにも気付けなかった。やがて、気付いた後も、それをどう解釈していいのか戸惑った。
力が弱ければドウコクに負ける。強くあらねば志葉家の者ではない。そう言われ続けているのに、丈瑠の視線が向くのは、いつも弱くて小さなモノの方だったことも、彦馬を困惑させた。この世を、人々を救うには、それらを思いやる優しい心が必要だ。しかし一方で、強さも追い求めないとドウコクには勝てない。
幼い丈瑠の純粋な気持ちを嬉しく思いつつも、彦馬はそれから眼を背けた。そして闘うためのモヂカラを覚えさせることに、注力した。
もしあの時、丈瑠が志葉家に入らなければ、丈瑠はどんな風に育っていたのだろうか。この一年間を共に過ごした、侍たち。流ノ介や千明の明るい雰囲気。自由な奔放さ。そして、それらが生み出す力があることを、彦馬は思い知った。力でも、技でもない。覚悟でもない。侍たちが持っていたもの。丈瑠にも、そんな力はあったはずなのに。それを自分が潰してしまっただろうことを考える度に、彦馬の胸はひどく疼くのだった。
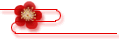
「ふう」
大きなため息をついた彦馬が、視線を丈瑠の布団に戻すと、丈瑠が目を開けて、彦馬を見ていた。
「お、殿!?」
高熱のためにうるんだ瞳で、丈瑠は彦馬を見上げる。
「お気が付かれましたか。何かお飲みになりますか?」
横に置かれた水差しに手を伸ばそうとする彦馬に、丈瑠は小さく首を振った。それを見た彦馬が丈瑠の前に座りなおすと、丈瑠もため息をつく。何事かと丈瑠を覗き込む彦馬を、丈瑠はじっとみつめた。そして一言
「爺の独り言がうるさい」
と呟く。
「お陰で目が覚めた」
頬を膨らませる丈瑠に、彦馬は苦笑いをするしかなかった。
「声に出しておりましたか、爺は」
言い訳する彦馬に、丈瑠の顔は不服そうだった。
「いやはや………申し訳ございません」
「それだけじゃなくて、全部、間違ってる」
間髪いれずに言うと、丈瑠は彦馬の反対側に、身体を傾けた。
「はっ?間違っているとは………」
顔が見えなくなってしまった丈瑠へ、首を伸ばす彦馬。
「………何が………でございますかな」
「だから、全部!」
丈瑠が言いきった。
「………全部?はて………」
彦馬が腕組みをして、天井を眺めながら考える。すると、苛立ったのか、丈瑠が声を荒げた。
「だいたい、シャボン玉じゃないぞ、あれは!!」
「………は?」
そこで初めて彦馬は、丈瑠の間違っているという指摘が、先ほどまでの彦馬の回想にあることを知った。
「これは………爺はどこまで声に出していたのか………」
「あれは、くらげだ!!!!」
きまり悪そうに呟く彦馬を無視して叫ぶ丈瑠に、今度は彦馬の目が点になった。
「く、くらげ………?」
明らかに疑問符のついた彦馬の言葉に、丈瑠が布団の中で振り返る。そして彦馬を睨み上げた。
「爺が言ったんだ!!爺が出せって!!だから、出したのに!!」
丈瑠の言葉は、どうにも彦馬には理解できず、彦馬はただ目を瞬くしたなかった。その様子を見た丈瑠が、唇を横一文字にする。その子供っぽい仕草に、思わず彦馬は噴き出しそうになるが、それをどうにか抑えた。
「殿。さすがに爺でも、殿に『くらげ』を所望することは………それも、あんな部屋を漂うようなおかしなモノを………」
「爺が!夜は暗くて、本を読めない………と言ったんだぞ!?」
そして丈瑠は、部屋の隅に置いてある和風の電気スタンドを指示した。
「俺があれと絵本を持って行ったのに、灯りの高さが合わないから、やっぱり読めないって!!」
そこまで言われて、彦馬もうっすらと思いだしたことがあった。
丈瑠にはテレビも見せなかったので、丈瑠の室内での楽しみと言えば、本を読むことくらいしかなかった。そしてもちろん、丈瑠はまだ字が読めず、彦馬の膝の上で、読んでもらうしかなかったのだ。しかし、この部屋はそれほど明るい照明はなく、彦馬も読みにくかったが、丈瑠の視力にも影響が出ないかと、彦馬は心配だった。だから、夜に本を読むのは、止めたかった。
「確かに………そのようなことを言った記憶はありますな。殿に膝の上で大泣きされて困った記憶も………」
「あの時、爺は言ったんだぞ!!光るくらげでも部屋に浮いていれば、明るくなって読める………って!!」
「………はああ?殿、それはないでしょう。爺はそんな意味不明のことは申しませんぞ。だいたい光るくらげとは何ですか?」
「爺が言ったんだ!!そういう絵本があって、海の洞窟の中が明るいんだ。それを読んだ時に、こういう『光るくらげ』がこの部屋にも浮いていれば、爺は夜も俺に本を読んでくれる、って!」
あまりのことに口がきけない彦馬に、丈瑠は苦々しい顔をする。
「覚えていない………のか」
小説 次話
2010.04.10